 may
mayこんにちは!おうち英語と知育を愛する母mayです。勉強だけで生きてきた母が『中学でネイティブみたいな発音をすると笑われるあの雰囲気』を撲滅したくておうち英語を広めようとやり方を発信中。簡単にできるおうち英語の取り組みをご紹介していますので、いいものがあればどうぞご一緒に!日本の子供達の未来が明るくなりますように。知育情報も発信しています!
⚫︎子どもにお金の教育をしたいけど、何からしたら良い?
⚫︎こどもにお小遣いってあげてる?
小学生になると「お小遣いをあげるべきか」「お金の教育はどう始めるか」と悩むご家庭は多いのではないでしょうか。実は、お金の教育は家庭で手軽に始めることができます。その一つが「本の予算管理」です!
私が小学生の娘と実際に実践している方法を具体的に書いていますので、
 may
mayお金も手間もそれほどかからず、手軽な方法なのでお金の教育の第一歩として一緒に始めていきましょう!
当サイトはamazonアソシエイト等のアフィリエイト広告を利用している記事があります。『自分に正直に真っ直ぐに生きること』をモットーに生きておりますので、本当におすすめのもののみを記事に載せます。本業でしっかり働きます!
本の予算管理とは?その仕組みと効果
本の予算管理とは、毎月決めた金額の範囲内で子ども自身に本を選ばせ、購入させる取り組みです。欲しい本が予算を超える場合は、次月までお金を貯めてから購入することもできます。この方法は非常にシンプルですが、子どもにとっては多くの学びがあります。
 may
may今まで絵本を買ってもらっていた娘は本の値段を知りませんでした。すると、本を大事に扱わず、無くしてしまうことが頻発。本の予算を管理することで物の値段を把握し、本当に欲しいものを厳選し、欲しいものを手に入れるまで我慢する感覚が得られます。金銭感覚を養うのにもってこいの取り組みです。
具体的な流れ
- 毎月の「本の予算」を決める(例:2,000円)
- 子どもが本屋やネットで本を選ぶ
- 予算内で本を購入する or 欲しい本が高い場合は予算を貯める
- 購入した本は大切に扱う
 may
may本屋に実際に行くのがおすすめです。『買い物に行って物を買わずに吟味する』いい経験になります。
本の予算管理で身につく力
1.お金の管理能力
自分で予算を管理し、計算しながら本を選ぶことで、自然と足し算・引き算の力が身につきます。また、「あと何ヶ月でこの本が買える」といった計画性も育まれます。
2. 物の価値を知る
本の値段を調べることで、「この本は高い」「この本は安い」といった価格感覚が養われます。さらに、消費税などについても自然と学ぶ機会になります。
3. 物を大切にする心
自分で選び、予算を使って購入した本は、与えられたものよりも大切に扱うようになります。失くしたり壊したりしないよう、より注意深くなります。
4. 選択と我慢の力
欲しい本が予算を超えていた場合、「今月は我慢して来月まで貯めよう」と考えるようになり、計画的な消費や我慢する力が身につきます。
5. 幸せの本質を学ぶ
たくさんの物を持つことよりも、「自分の好きなもの・本当に欲しいものに囲まれること」が幸せであると実感できます。
 may
may物欲はキリがないもの。子供の頃から物にとらわれすぎず、自分の幸せについて考えてもらえると嬉しいですね
お小遣いとの違い
お小遣いは「貯めること」が主な目的になりやすいですが、本の予算管理は「いかに上手に使うか」「選択するか」に重きがあります。どちらも大切な金融教育ですが、本の予算管理はより実践的な消費体験を通じて学ぶことができます。
 may
mayお金は上手に使う方が難しくないですか?大人も考えさせられる内容。。。
本の予算管理のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
○計算力や計画性が身につく ○価格や税金などの知識が自然と増える ○物を大切にするようになる ○自分で選ぶ経験ができる | ✖️予算内でしか本が買えないため、欲しい本がすぐに手に入らない場合がある |
 may
may我が家では英語絵本は私が買うので冊数制限はありません。自分で欲しがるのは日本語の娯楽絵本なのでそこだけ予算管理してもらっています。
実践のポイントと体験談
用意するもの
- 毎月の本の予算(現金または電子マネー)
- 本人が選んだ本と値段を記録するノート(お小遣い帳)やアプリ
 may
may我が家ではダイソーのお小遣い帳を利用しています!(上の画像から見れます)通帳風の見た目がポイントで娘もすごく気に入っています。

実際の管理方法
- 本のジャンルや種類は自由。子どもの意思を尊重し、選択の失敗も経験として受け入れる
- 予算は2,000円程度が目安。
- 購入した本は記録し、読み終わった後の感想も書かせることで、読書習慣と自己表現力も育てる
 may
may2000円って絶妙な値段で1冊は買えるけど、二冊は買えません。1ヶ月に一冊は本を読んで欲しい私の思惑がここに反映されています.
実際に買った本の例
買った本の一例になります。周りの子も教育熱心なご家庭が多いようで、知育になるような本を欲しがります。(ラッキー!)科学や生物、歴史に特化した本も多く、本で学べる範囲も広がります。
さらに広げる応用編
電子マネーでの管理
現金だけでなく、電子マネーでの予算管理もおすすめです。近年は電子マネーの利用が増えており、子どものうちから電子マネーの使い方や「見えないお金」を管理する感覚を身につけることが重要です。使いすぎを防ぐためのルール作りも一緒に考えましょう。
お小遣い貯蓄プラン
今後は「貯金すると得になるお小遣い制度」も導入予定です。お年玉やお小遣いを貯めて、年に一度利子をつけて返すことで「複利」の仕組みを体感させることができます。金融リテラシーを高める絶好の機会です。
 may
mayお金の教育を始める前にお子さんに読んでもらうといいのがこの本です。お金の基本や投資の仕組みなどがわかりやすく説明されています。にゃんこ大戦争もたっぷり入っていて飽きがこないです。
まとめ:本の予算管理で始める家庭の金融教育
本の予算管理は、難しい準備や高額な費用がかからず、家庭で手軽に始められる金融教育・知育法です。お金の使い方や物の価値、選択の力を身につけるだけでなく、読書習慣も同時に育てることができます。お子さんの成長に合わせて、現金から電子マネー、貯蓄制度へとステップアップさせていくのもおすすめです。
 may
may貯めることも使うことも大事!使うに焦点を当てた知育でした!
家族旅行を知育にしたのがこちらの記事です子供も旅行計画に巻き込んで思い出を倍増させましょう↓

その他知育っぽいことはこちらにまとめています!手軽に始められるものが多いので取り入れてみてください↓
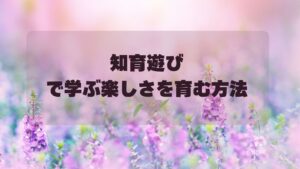
おうち英語もやっています。子供が英語絵本を音読できるようになるまでのロードマップはこちら↓
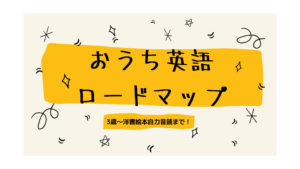
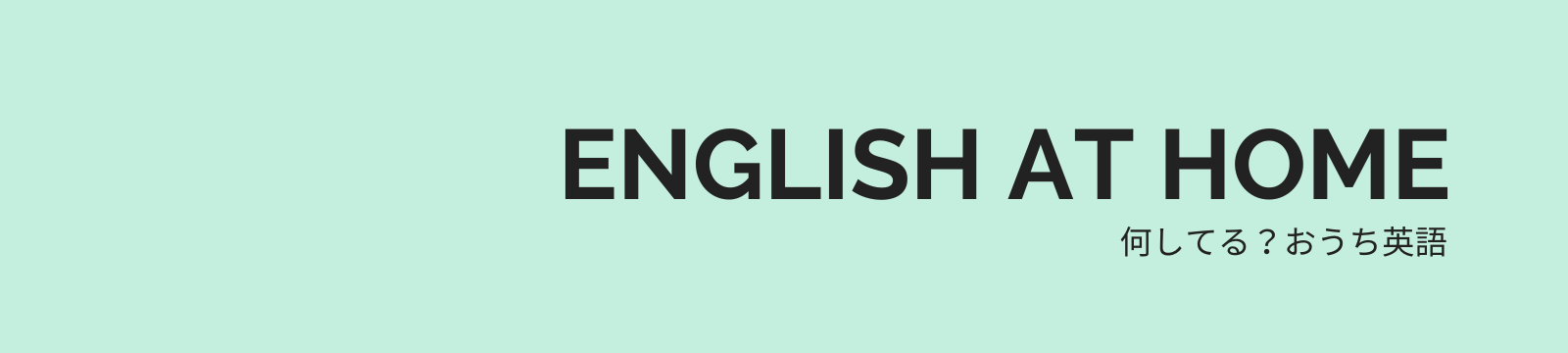
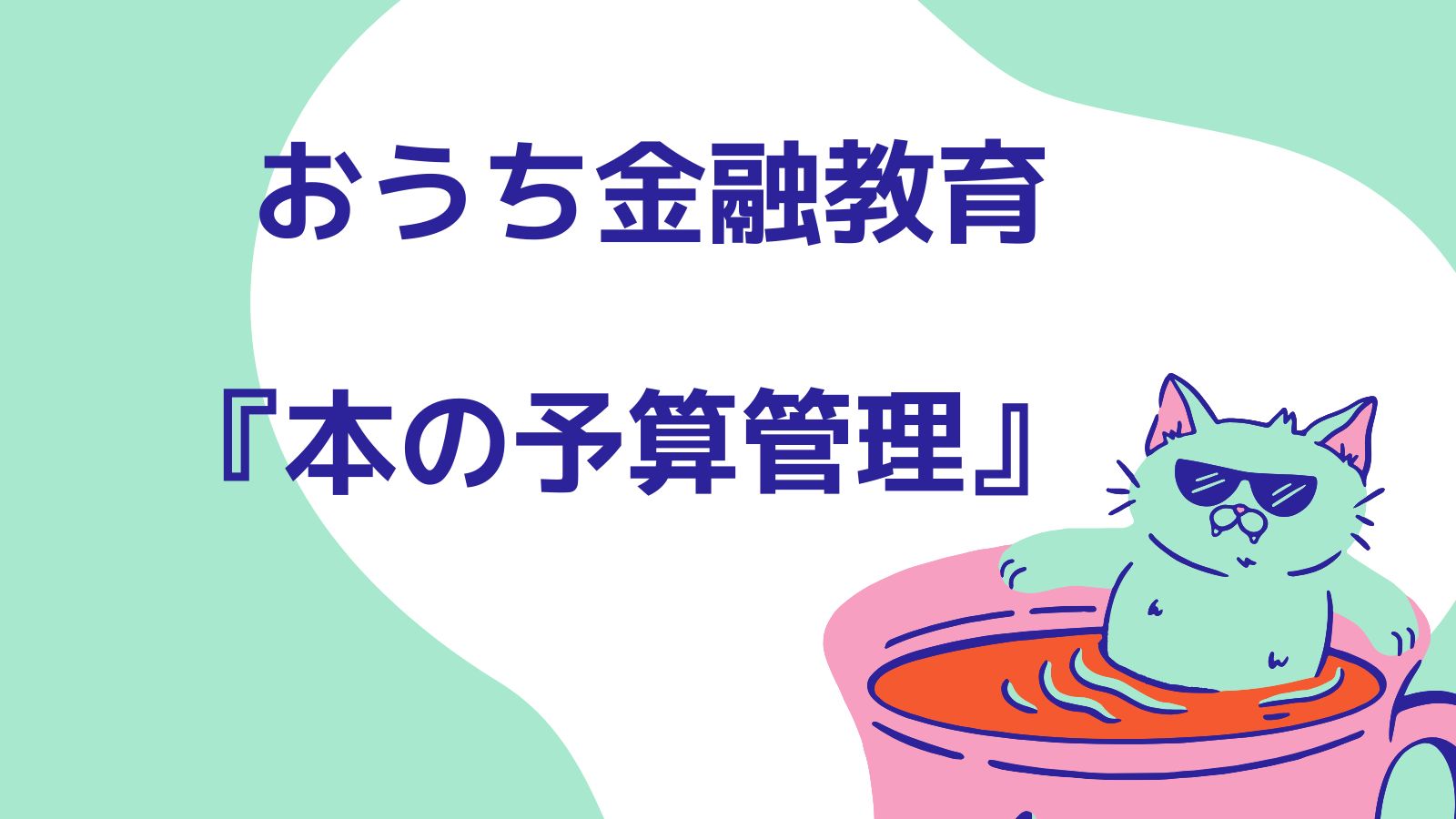




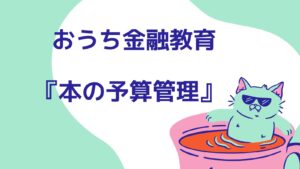
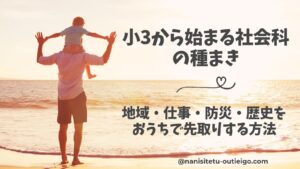


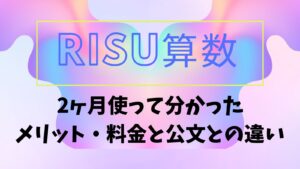




コメント